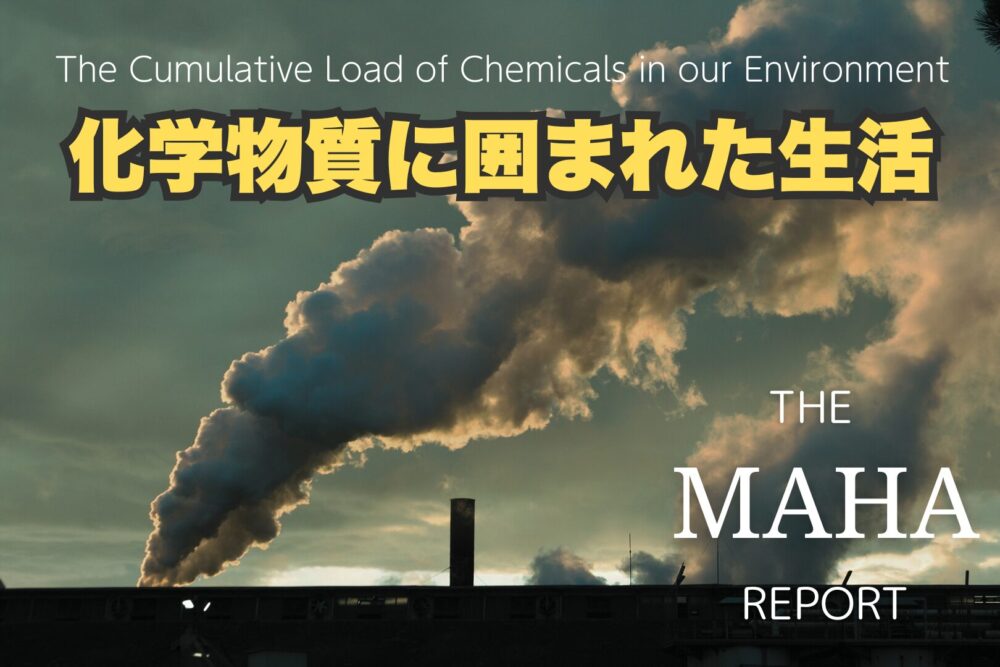この記事は、アメリカ政府が発表した「MAHAレポート(Make Our Children Healthy Again)」をもとに、現代の子どもたちを取り巻く健康リスクを読み解く全5回シリーズの第3回です。
今回は、「空気・水・土・日用品」といった私たちの身の回りに潜む化学物質の蓄積が、子どもの発達や健康にどのような影響を及ぼしているか──目に見えない“負荷”として蓄積する化学物質のリスクについてを詳しく見ていきます。
子どもたちは“環境のスポンジ”である
MAHAレポートは、化学物質のリスクが特に子どもにとって深刻である理由を以下のように示しています。
- 呼吸数・摂取量が体重比で大人より多い
- 発達途上で解毒機能や代謝が未熟
- 神経系・内分泌系が急速に成長しており影響を受けやすい
つまり子どもは、環境中の化学物質をより多く、より敏感に吸収してしまうのです。
私たちの生活環境に潜む化学物質とは?
以下のような物質が、家庭・地域・学校などあらゆる環境で検出されています。
| 化学物質の種類 | 主な用途・発生源 | 健康影響の懸念例 |
|---|---|---|
| PFAS(有機フッ素化合物) | 撥水・撥油加工、テフロン調理器具、防水スプレー | 免疫抑制、内分泌かく乱、発がん性 |
| フタル酸エステル類 | プラスチック製品、柔軟剤、香料 | ホルモン撹乱、男性不妊、行動異常 |
| 重金属(鉛、水銀、カドミウム) | 老朽化した水道管、魚介類、産業排水 | 神経発達障害、IQ低下、腎障害 |
| 農薬残留物 | 果物・野菜の残留農薬 | ADHD、神経毒性、生殖発達リスク |
MAHAレポートでは、これらの化学物質が「単体ではなく複合的に蓄積する」ことが問題の本質であると指摘しています。
マイクロプラスチック問題は日本でも取り上げられますが、海だけでなく大気中にも含まれるということなので、子供への影響が心配されます(地球となかよし)。
“安全”の基準は、子ども向きではない?
日本を含め多くの国では、化学物質の安全性評価が成人男性を基準にして設定されてきました。しかし、実際に最も感受性が高いのは胎児期〜乳幼児期の子どもたちです。
たとえば、以下のような問題が指摘されています。
- 「許容量以下」とされる水道水のPFASでも、子どもでは免疫応答の低下が見られた事例あり(出典:US Right to Know, 2023)
- 母体の体内に蓄積した化学物質が、胎盤や母乳を通じて乳児に移行することが確認されている(出典:Clinical Lab, 2023)
- 香り付き柔軟剤などに含まれる成分が空気中に揮発し、乳幼児の呼吸器を刺激するリスクも指摘(出典:PubMed, 2000)

つまり「大人が平気だから子どもも安全」とは限らないのです。子ども特有の感受性を前提とした規制や製品設計が必要であることが、MAHAレポートの大きなメッセージの一つです。
日本も“化学物質天国”ではないのか?
日本では以下のような実態から、化学物質に関する規制や実態把握が遅れているとされます。
- PFAS*の規制基準は2024年にようやく「1リットルあたり50ng」に暫定設定(NIHON DRAIN)
- EUで禁止されているネオニコチノイド系農薬や添加物が日本では使用継続中(EcoNetworks)
- 消費者表示の縛りが緩く、「香料」「調味料(アミノ酸等)」などの成分名非表示が許容(東京都)
*化学物質PFAS(ピーファス)による水道水の汚染により、動脈硬化、がん、糖尿病、大腸炎などの原因とされる

また、学校や保育園で使用される除菌スプレー・芳香剤なども、子どもの化学物質曝露源となっている可能性があります。
どう向き合う?家庭でできる5つの工夫
すべての化学物質を避けることは現実的ではありませんが、次のような生活習慣の見直しで“蓄積の総量”を減らすことが可能です。
- プラスチック容器での電子レンジ加熱を避ける
- 水道水は浄水器や煮沸を併用する
- 香り付き柔軟剤や消臭スプレーの使用を減らす
- 有機野菜や減農薬野菜を選ぶ
- 魚介類は種類を分散し、水銀リスクの高い大型魚を控える
そして何より、「目に見えないからこそ存在を意識する」ことが予防の第一歩となります。
まとめ:子どもたちの“見えない健康格差”に目を向けて
MAHAレポートは、化学物質が「目に見えない形で子どもの身体に蓄積し、将来の健康と発達に影響する」と警鐘を鳴らしています。結果として、以下のリスクを増幅させているとしています。
- 集中力の低下
- 慢性的な免疫低下
- 学力・社会性の格差
こうした問題の背景には、化学物質が生活環境に入り込んでいる──それがレポートの根幹にあるメッセージです。誰もが薄々感じていたことで、この流れは止めることは不可能と思っていたことでしょう。
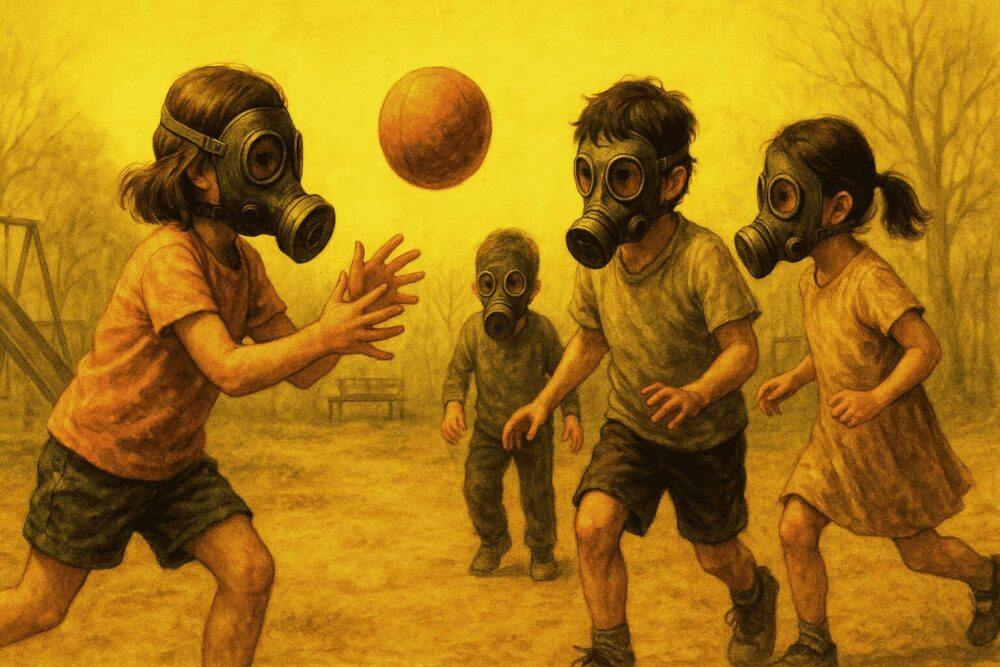
科学先進国のアメリカが、これまでの方針を覆す方向で行政を改革しようとしています。トランプ氏とケネディ氏は口だけではなく、政治的目標を実現するために本気で推進しています。
次回(第4回)は、「スマホ依存が子どもの集中力を低下させる?」について取り上げます。アメリカ同様、日本でも日々話題になるこの問題について学んでいきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
Source: The MAHA Report