私の好きなアーティストESOWさんの展覧会が台北で開かれています(2025年12月13日まで)。TARTCH Galleryというモダンなギャラリーだそうです。
彼は17歳でアメリカに渡り、スケボーやグラフィティ(落書き)などに触発され、現在は浅草を拠点に作家活動をされています。台湾では、日本のアートや文化の人気が相変わらず高いですね。
日本と台湾は、地理的にも文化的にも近く、旅行先としても人気があります。しかし、人口構造や経済の稼ぎ方、生活コストの実感には大きな違いがあります。
本記事では、人口・経済・所得・物価・教育の5つのテーマから、台湾と日本のリアルな違いをデータと社会背景をもとにわかりやすく比較していきます。
人口構造:日本は“超高齢社会”、台湾は“急速な少子化”
まず最もわかりやすい違いが人口です。日本の人口は約1億2,300万人と台湾の約5倍ですが、直面している課題は驚くほど似ています。どちらも深刻な少子高齢化に悩んでおり、社会保障や経済成長に影響を与えています。
| 国名 | 人口 | 高齢化率(65歳以上) | 合計特殊出生率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 約1億2,300万人 | 約29% | 約1.2 |
| 台湾 | 約2,300万人 | 約19% | 約0.8(世界最低クラス) |
日本はすでに高齢化率が約29%に達しており、世界でも最も高齢化が進んだ国です。一方、台湾は高齢化率では日本ほどではありませんが、出生率が0.8台と世界でも最低レベルで、人口減少が急速に進みつつあります。
台湾は2025年に超高齢社会に突入すると見られており、日本がすでに経験した社会課題に短期間で直面する可能性があります。

両国とも人口減少が不可避である点は共通していますが、台湾は変化の速度が非常に速いのが特徴です。
経済と産業:日本は“多角型”、台湾は“半導体特化型”
経済規模で考えると、日本は名目GDPで世界第4位(約600兆円)。台湾はおよそ130兆円規模です。国家規模では日本が圧倒しますが、重要なのは稼ぎ方の構造です。
| 指標 | 日本 | 台湾 |
|---|---|---|
| 名目GDP規模 | 約 600兆円 | 約 120兆〜135兆円 |
| 一人あたりGDP | 約 555万円 | 約 525万円 |
| 主な産業 | 自動車、機械、化学、観光、サービス | 半導体(TSMC)、電子部品、IT製造 |
日本は自動車、機械、化学、サービス業など産業が多様で、巨大な内需市場を持っています。対して台湾は、TSMCを代表とする半導体産業に圧倒的に依存しており、世界のITサプライチェーンの中心として機能しています。
半導体の輸出依存度が高いため、世界景気に左右されやすいというリスクもありますが、高付加価値産業に集中している強みもあります。日本のかつてのお得意分野がごっそり台湾に移った感じです。
一人あたりGDPを見ると、台湾は近年日本に急接近しており、近い将来に逆転するシナリオすら現実味があります。日本は1995年から低成長が続く一方、台湾は小規模ながら「伸びる領域」に特化した戦略で国際競争力を高めています。
(1米ドル・150円で換算)
所得と格差:平均は近いが“中央値”に差がある
所得を比較すると、平均賃金そのものは日本と台湾で大きく異なるわけではありません。日本の平均年間賃金はOECD基準で約460万円、台湾の平均月収は約30万円で、年収換算すると水準としては近い数字になります。
| 指標 | 日本 | 台湾 |
|---|---|---|
| 平均年間賃金 | 約460万円 | 約364万円(男約410、女約290) |
| 平均月収 | 約31〜33万円 | 約30万円(NT$60,000) |
| 月収中央値 | 約25万円前後 | 約¥19万〜20万円台 |
しかし、暮らしの肌感覚に大きく影響するのは中央値です。台湾は平均値と中央値の差が大きい、つまり格差が広がっているという指摘が多くあります。

平均月収30万円に対し、中央値は150万~200万円台というデータもあり、多くの若者が平均より下で生活している現実があります。大手グローバル企業の給与は高く、国内中企業との給与差が広がっています。
日本も実質賃金が長年伸び悩んでいますが、台湾のほうが所得格差が生活実感として強く意識されやすい状況です。「給料は上がっても家賃と物価が追いついてしまう」という声も台湾の若者からよく聞かれるようです。
出典: FOCUSTAIWAN
物価と生活コスト:東京は高いが、台北も急上昇中
「台湾は安い」というイメージは、すでに過去のものになりつつあります。外食や家賃が上昇し、都市部の生活コストは日本の地方都市と大きく変わらないどころか、台北中心部では日本より高いケースも出てきています。
Numbeoの生活コスト指数(2025年頃)では、東京のほうが台北よりやや高いものの、その差は想像以上に小さい結果になっています(NumbeoはNYを100としたスコア、パリは74.6)。
| 都市 | 生活費指数(家賃除く) | 家賃指数 | 総合コスト感 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 約51 | 高い | 全体的に高い |
| 台北 | 約47 | 急上昇中 | 近年値上がりが著しい |
特に台北の家賃は上がり続けており、現地の若い世代は「給料より家賃の伸びが速い」と感じています。日本は円安で“安い国”と言われますが、生活コストで見ると「東京>台北」の構図は維持されつつも、差は縮小を続けています。
総合すると、生活しやすさの面では
日本=生活コストが比較的安定、台湾=物価上昇が速くプレッシャーが強い
という評価に落ち着きます。
教育と若者の進路:日台とも学力上位だが、方向性が違う
教育は両国の特徴が最もよく表れる分野です。日本と台湾は国際学力調査(PISA)で常に上位に入り、「勉強熱心な社会」「受験文化」が共通しています。
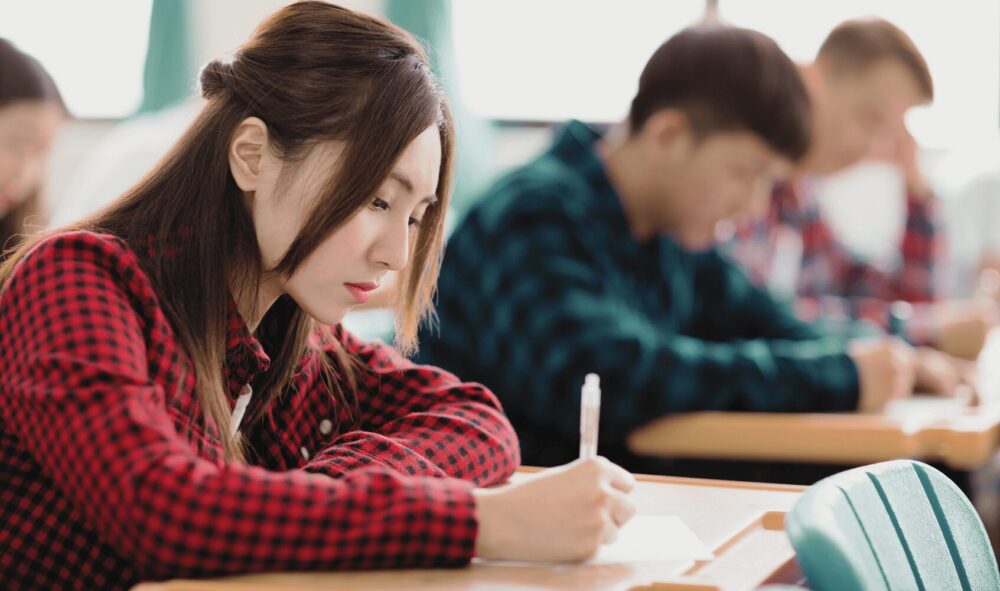
しかし、教育の方向性には違いがあります。
- 日本:均質な基礎学力、部活動や学校行事も重視
- 台湾:数学・理科・IT教育が強く、STEM重視の傾向が顕著
| 項目 | 日本 | 台湾 |
|---|---|---|
| 義務教育 | 9年 | 9年→12年(高校無償化へ移行) |
| 学力(PISA) | 数学・読解で上位 | 数学・理科が非常に強い |
| 若者の進路 | 大企業・公務員の安定志向 | IT・スタートアップ志向が増加 |
台湾では、IT企業やスタートアップを目指す若者が増えており、教育もそれに合わせて変化しています。一方、日本の若者は依然として大企業・公務員といった“安定志向”が強く、進路選択にも社会構造が反映されています。
若者の価値観に関しても、台湾は政治や社会問題に対する関心が高く、SNSや選挙活動で積極的に意見を発信する傾向があります。日本では政治参加が低調であることを考えると、この部分は最も大きな違いと言えるでしょう。
資料:OECD
似ているようで違う2つの国
日本と台湾は、文化的な親和性や民主主義、アニメやスポーツなど共通点の多い国です。しかし、数字で比較するとかなり違うことがわかります。特に人口差がこれだけあるとは思いませんでしたし、経済的にも日本が追い越されているとの認識でした。
最後に、野球のライバルである両国をプロ野球選手の年棒で比較したいと思います。
| 項目 | 日本・NPB | 台湾・CPBL |
|---|---|---|
| 最低年俸(1軍/トップリーグ) | 1,600万円(1軍最低年俸)(Wikipedia) | 約420万円(2009年)(en.cpbl.com.tw) |
| 平均年俸(全体) | 約4,470万円(2023年)(Japan Truly) | 約950万円(2017年)(en.cpbl.com.tw) |
| 最高クラスの年俸 | 歴代最高:田中将大 9億円(楽天時代のNPB契約)(Japan Truly) | 歴代最高:張育成(Yu Chang)約1.2〜1.3億円(Taipei Times) |
データが少し古いところもありますが、ここには歴然とした差がありましたね。この理由は技術力もありますが、日本の人口が5倍ということでしょう。

2024年の日本のプロ野球、NPBの年間観客動員数は2,674万人、台湾のCPBLは300万人とのことです。観客数は9倍近くにもなるんですね。人口が多いと個人間の競争も激しくなり、結果的に国力も上がるということなんでしょうか。アメリカのビジネスやスポーツにおける国際競争力を見ていると、納得させられるところがあります。
最後までお読みいただきありがとうございました。












