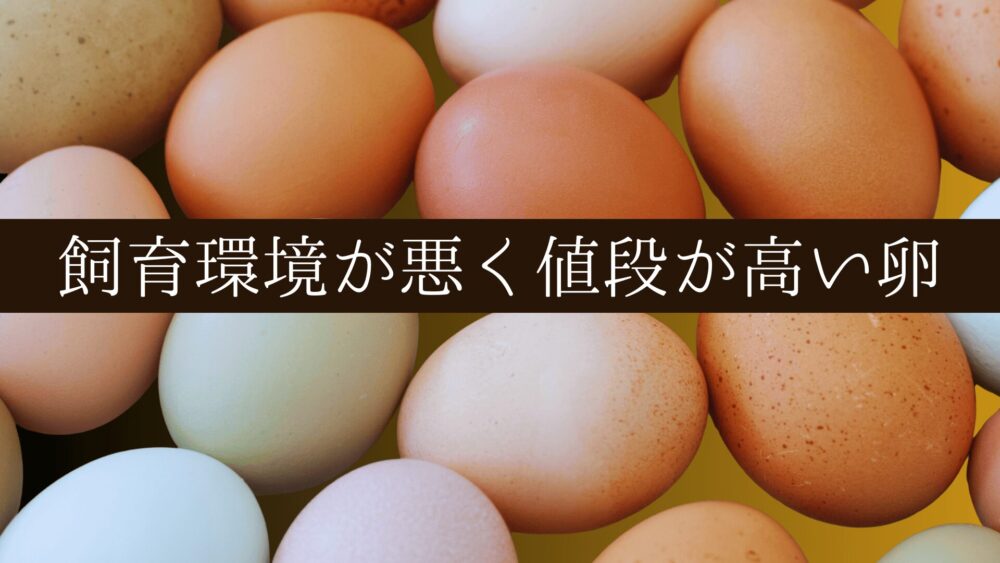「最近、卵が値上がりした?」——家計のやり繰りは、どこの国でも共通の話題です。為替や飼料高に目が行きがちですが、値段の背景には鶏の暮らし方(ケージ・平飼い)や、国ごとの衛生ルール、小売の販売方法までが絡んでいます。
日本では卵は安くて当り前という常識がありますが、卵を産んでくれる鶏や人間の健康に問題はないのでしょうか?探ってみたいと思います。
海外と価格を比べてみると
国によってパックの入り数が違う(日本は10個、米英は12個、韓国は30個が多い)ので、1個当たりの価格で比較します。
- 日本:10個 314円 → 1個 31.4円/12個換算 377円
- 米国:12個約 529円 → 1個 $0.30 ≒ 44円($1=147円)
- 韓国:30個 約751円 → 1個 約₩236 ≒ 25円(₩1=0.106円)
- スペイン:12個約 445円 → 1個 €0.217 ≒ 37円 (€1=171円)
欧米は卵の価格がものすごく高いと思っていましたが、他の消費財との価格差を考えると大した差ではありませんね。
因みに、一人当たりの年間消費量は、日本が339個、アメリカが287個、韓国が278、スペインが143個とのことです。
日本は生食重視と古い鶏舎が特徴
日本の鶏卵は洗浄・殺菌・選別・冷蔵流通を徹底し、生卵を安心して食べられる仕組みを築いてきました。これは世界的にもユニークな強みだそうです。
一方で、鶏の行動が限られる従来型ケージが今も主流で99%(Hope Animals)。欧米で意識される止まり木・巣・砂浴びといった“鶏らしい行動”が取りにくく、エンリッチド(改良)ケージや平飼いの比率はまだ低いままです。

導入が進まない理由は、①改修投資が大きい、②高温多湿×生食文化ゆえの衛生要件が厳しい、③価格転嫁ができない、の三つがよく挙げられます。
福祉の観点から拡大する飼育スペース
EUでは動物福祉の観点から、2012年に従来型(バタリー)ケージを全面禁止しました。EFSA(欧州食品安全機関)が非ケージ推奨を含む科学的意見を提示。行動要求(止まり木・砂浴び・巣)や骨折低減などを重視しています。
現在はエンリッチド(改良)ケージと代替(平飼い等)が合法とのことですが、さらに“脱ケージ”を求める市民運動が継続しています。拡張とはいえ、所詮ケージなので環境はさほど変わりません。

アメリカは州法で「州内で売る卵はケージフリー」を広げ、主要小売店も追随。カリフォルニア、マサチューセッツ、オレゴンなど8州が“販売規制型”でケージフリー義務化しています。
オーストラリアやニュージーランドも期日を切って移行中です。スピードは国により違いますが、“より動ける鶏舎”へ向かうベクトルは世界共通と言えます。
出荷時に殻を洗う日本と洗わないEU
いまの日本は、GPセンター(選別・パック詰め工場)での洗卵・消毒+農場での衛生管理(ワクチン等)を組み合わせ、殻表面の汚染を大幅に低減しています。ただし菌はゼロではないため、生食は賞味期限内+冷蔵が前提という設計です。
一方、洗浄で卵殻のクチクラ(保護膜)が薄くなるため、温度管理・乾燥・殺菌を適切にしないと逆に侵入リスクが上がるため、手間がかかるそうです。

EU等の洗わない方針の場合、クチクラを保持でき、殻のバリア機能を活かせる。洗卵設備や店頭までの冷蔵が不要な分、工程が簡素でコストを抑えやすいそうです( EUR-Lex)。
また、店頭では常温販売が基本のため、品質劣化の管理(時間・温度の一貫性)が鍵となり、購入後は家庭で冷蔵が推奨されるとのことです。
飼育方法による品質の違い
栄養価の点では、“飼い方”より飼料設計と鮮度の影響が大きいのが実際です。例えばオメガ3強化飼料や日光を浴びる環境で、ビタミンDやオメガ3がやや高まる商品はあります。
黄身色はパプリカやトウモロコシなど餌由来の色素で変わるため、「濃い=必ずおいしい」ではありません。平飼い・放牧は運動や採食の違いで風味の個性が出やすい側面があり、卵かけご飯の“香りの好み”で選ぶ楽しみもあります。

鶏と言えばインフルのリスクが常にありますが、ワクチンはケージかケージフリーかではなく、その飼い方で生じる“感染リスクの種類”と各国の規制で決まるそうです。
ケージフリーは環境接触が増える分、必要となるワクチンや寄生虫対策が広がる傾向があります。平飼い=より健康的と考えていましたが、これは以外な発見でした。
日本のケージフリー化はなぜ進まない?
日本のケージサイズが小さいまま、或いは平飼いが進まないのは、消費者と流通の低価格志向と制度の設計が合わさった結果だそうです。
- 消費者・流通の都合(低価格志向)
卵はスーパーで最強の目玉商品。週替わりの特売、10個パックの均一価格、外食・中食の大量需要が低価格競争を固定化させました。“1個数円の差”が売れ行きを左右するため、設備投資が必要な鶏舎への上乗せ価格が浸透しにくい - 制度・業界構造
行政が生産者の衛生・災害対策や飼料価格安定は手厚く支えつつ、動物福祉の最低基準やラベル表示は欧州ほど強制力がありません。結果として、量と衛生は支えるが、福祉への投資は現場任せになりやすい。これが投資の踏ん切りを鈍らせ、移行を遅らせている

稀に10個で200円前後のものを見かけます。こんなに安くて大丈夫なのかと毎度思います。大手だと、1日の生産量が300万個などと聞いたことがあります。鶏のストレスたるや、半端ではないと想像します。
知っておきたい卵用鶏の寿命
金額や産地だけではなく、その卵がどのように作られたのかを知る必要があると思いました。特に卵は機械で製造されるものではなく、生産性が最大化できるよう鶏の身体を人工的に操作しているからです。
日本では通常、約74週齢(およそ520日)を目安に廃鶏となり、僅か1年半の命を終えます。産卵数・殻強度・体調の総合指標が落ち始める節目という理由です。欧米でも80週程度なので、ここは世界共通です(Farmars Weekly)。

近年は系統改良と栄養管理で80→100週の長期化も研究されているそうです。だとしても、たったこれだけの人生(鶏生?)をケージの中だけで過ごすというのは過酷だと思いました。
せめて、国が平飼いを制度化し、我々に美味しい卵を提供してくれる鶏たちが、喜怒哀楽のある生活ができるようになるよう、動物福祉的配慮が必要と思いました。
現在、欧米のケージフリー卵の価格と日本のケージ卵の価格がほぼ同じということは、日本でも大幅な価格上昇をせずに実現可能ということではないでしょうか。(日本の平飼い卵はより高く、現状10個で約500~600円)
最後までお読みいただきありがとうございました。