何が起きている?——IEAと「3倍目標」の背景
日本では今、あちこちで国立公園や野山を切り開いて、太陽光パネルの設置工事が進められています。メガソーラー建設のニュースが流れる度に反対の声が湧き上がり、再エネ=悪者のイメージが広がりつつあります。
再エネは私たちの生活に必要なのでしょうか?そして、そもそも何を目指しているのでしょう。この世界的な流れの背景には、IEA(国際エネルギー機関)という組織の存在があります。
IEAは1974年のオイルショックをきっかけに生まれた政府間の参謀役です。加盟国は原油を90日分備蓄し、緊急時に協調対応する仕組みを持ちます。IEAには世界を統括する権限はなく、データ分析と提言で各国政策に影響を与える存在だそうです。(IEA)

2023年のCOP28では、2030年までに再エネ容量を世界で3倍、省エネ改善率を2倍にする方針が共有されました。これは政治的合意であり、IEAは達成に必要な条件(送電網や蓄電の量)を数字で管理をしています。(UNFCCC, COP28)
ボトルネックはどこ?——送電網と蓄電の遅れ
いま世界では、発電施設はできても送電と蓄電が追いついていないのが最大の課題です。
- 系統接続の待ち行列:少なくとも1,650GWの案件が先進段階(用地確保、系統接続検討中など)で接続待ち。全体では3,000GW規模という推計もあり。(IEA, Global Renewables Alliance)
- 送電網の増設・更新:2040年までに8,000万km(いま世界にある送電網“まるごと”に匹敵)。2030年まででも2,500万km規模が必要と報じられている。(IEA Blob Storage, Reuters)
- 蓄電の拡大:2030年に1,500GWの蓄電が目安。内訳は電池が1,200GWで、年平均+25%**ペースの導入が必要。(IEA)

この「接続・送電・蓄電」に投資が追いつくかどうかが、3倍目標の成否を左右します。IEAも“グリッドが遅れると再エネは進まない”と繰り返し指摘しています。
供給の現実——なぜ中国が強い?
太陽光モジュールの製造は中国に地理的に集中しています。IEAによれば、ポリシリコン~セル~モジュールの各工程で中国のシェアは80%超です。規模の経済と投資の大きさが、圧倒的なコストにつながっています。
一方で各国は中国依存度を下げようと動いています。アメリカは中国製セル・モジュールの関税を25%→50%に引き上げ、EUも産業政策で域内製造の回復を目指しています。
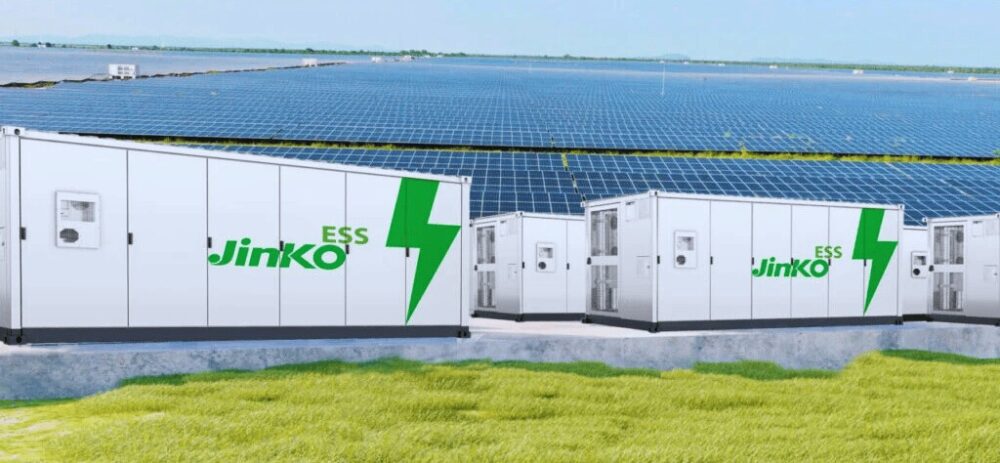
〈2024年モジュール出荷 トップ5(InfoLink集計)〉
世界トップ5の合計出荷は約502GW。上位4社だけで約6割超を占める“寡占”の色が濃い年でした。(InfoLink Group, TaiyangNews – All About Solar Power)
| 順位・企業 | 本社 | 主な生産国 | 世界シェア(%) |
|---|---|---|---|
| 1. ジンコソーラー | 中国(上海) | 中国、マレーシア、ベトナム | 約14.2%(出荷99.6GW÷703GW) |
| 2. ロンジ・グリーンエナジー | 中国(西安) | 中国、マレーシア | 約8.7–10.1%(推定61–71GW) |
| 3. JAソーラー | 中国(北京) | 中国、ベトナム | 約11.3%(出荷79.45GW÷703GW) |
| 4. トリナ・ソーラー | 中国(常州) | 中国、タイ、ベトナム | 約9.4–10.0%(推定66–70GW) |
| 5. トンウェイ・ソーラー | 中国(成都) | 中国 | 約6.5%(出荷45.71GW÷703GW) |
ジンコソーラーの直近の売上高は、約2兆円、ニューヨーク株式市場にも上場しています。
制度と評判――推進ムードは続くが、実現性が不透明
再エネ推進の掛け声は続きますが、“前提”が未整備なのが現状です。各国は安全保障・経済性・産業戦略の理由から再エネ拡大に賛成しました(COPの政治合意)。
前述の通り、現場の最大のボトルネックは送電網と蓄電で、ここが解消されなければ目標は達成できません。政策の潮流は「推進しつつ選別」ですが、米欧の足並みは完全一致ではありません。
米国は国内製造優遇・関税・人権トレーサビリティで“早く・強く”を志向する一方、EUは域内製造のてこ入れと製品基準(CFP・エコデザイン等)で“選びながら進める”姿勢で、加盟国ごとの運用や立地ルールに温度差があります。

世論は概ね支持でも、送電線ルート・料金設計・立地の段になると反発が起きやすく、「作れるのに、つなげない/貯められない」ギャップが進捗を鈍らせています。
要は、①系統投資の前倒し、②系統・配電側の蓄電と需要応答の拡充、③調達の透明化と多様化、④屋根優先と合意形成を“セット”で回せるかが実行可能性のカギです。
これからの電源ミックス
結論として、送電網と蓄電への投資が進む地域では、太陽光・風力が主役になり得ます。逆に投資が遅れる地域では、原子力やガス(CCUS)・水力の比重が長く残る“混合型”が現実的です。IEAの長期シナリオでは、2050年に再エネが発電の太宗を占める将来像が示されています。(IEA Blob Storage)
よくある疑問❓
- Q:太陽光は“主役”にならないのでは?
A:地域次第です。鍵は送電網と蓄電。ここに投資が進めば主力化し、進まなければ原発・ガス等が補完します。 - Q:なぜ中国だけが得をするのか?
A:製造は中国に80%超集中で価格優位ですが、米欧は関税・産業政策で多様化を進めています。短期はコスト上昇も、中長期は供給の分散が進む可能性があります。(IEA, The White House) - Q:3倍目標は現実的か?
A:発電所の建設は速い一方、接続待ちが少なくとも1,650GW、必要な送電網が2030年までに約2,500万km、蓄電は1,500GWと足りていません。ここを前倒しできるかが分かれ目。
小泉進次郎氏が環境大臣の2021年に、しきりに「再エネを2倍に増やす」という目標を口にしていたのを思い出しました。この再エネ騒ぎにはずっと懐疑的、胡散臭さを感じてきましたが、国際的な目標が背景にあったということがわかりました。
しかし国民の側からすると、なぜ突然メガソーラーの工事が一斉に始まったのか、という認識であり、政府や都道府県からの説明が不十分なことは明らかです。
いかに正当な理由があろうとも、何をしても許されるものではありません。巨額な税金の使途と、自然や環境への影響についての説明と合意が必要です。

特に、太陽光パネル市場は中国メーカーが圧勝であり、結果的に政府や自治体の利権・キックバックが疑われ、先進段階(パネル工事)の実現ですら雲行きが怪しくなってきたのが現状です。
この記事は、世間を騒がせている再エネとは何か?の疑問を発端に思考を始めたのですが、最終的に日本の政治・行政の一方的で強引な進め方により、ハードルを更に上げてしまったことが明らかになりました。
最後までお読みいただきありがとうございました。












