最近、アメリカの SNAP(補足栄養支援プログラム) に関連して、ローリンズ米国農務省(USDA)次官補が X(旧Twitter)上で、「農家からの直送生鮮食品をSNAP受給家庭向けに拡大する試験プログラム」 を近く開始する意向を示しました。
この動きは、受給者への支援を「購入助成」から「物品供給」へと転換する試みであり、まさに“無料の果物・野菜・肉・穀物を受給者に提供する”というSNAP改革の核心部分を反映しています。
制度設計の段階では、地域農業との連携や物流網の整備、対象家庭の選定方法の透明性などが課題になるとみられますが、アメリカ国内では「健康と食の安全を守る新しいステージ」として注目を集めています。

アメリカでは、現在約3,800万人が貧困ライン以下の生活を送っており、「何を食べられるか」が健康格差の象徴となっています。SNAPはかつて“フードスタンプ”として知られ、長年にわたってアメリカの食の安全保障の柱を担ってきました。
しかし近年、支援の「量」だけでなく、支援する「食の質」が問われ始めています。加工食品中心の食生活や、肥満・糖尿病の増加といった深刻な状況を背景に、SNAPを「健康」と「雇用」をも結ぶ制度へと再設計すべきだ、という改革論が再び注目されつつあります。
SNAP制度とは?──アメリカの食料支援の仕組み
SNAPは、連邦政府が実施する低所得者向けの食料補助制度で、対象者は電子カード(EBTカード)を使ってスーパーや市場で食品を購入できます。現在、約4,000万人以上が利用しており、年間予算は約1,200億ドル(約18兆円)に達します。
High calorie family in Los Angeles says they’re “afraid” now that SNAP is running out of money.
— johnny maga (@_johnnymaga) October 31, 2025
“We didn’t ask for these kids… and what are we going to do?”
Everything wrong with the American welfare system summed up. pic.twitter.com/XZVkxktVIY
目的は「飢餓の防止と最低限の栄養確保」ですが、現実には冷凍食品や加工食品の購入が中心になりやすく、「健康的な食材を選びにくい」という課題があります。
制度が機能している一方で、栄養格差の拡大や医療費増大の一因になっていると批判する専門家も多く、議会ではたびたび「支給対象を制限すべきか」「栄養教育を組み合わせるべきか」といった論争が起きてきました。
なぜ従来のSNAPは機能しなかったのか──政治と産業の壁
SNAPの課題は、単なる運用上の問題ではなく政治的・構造的な要因にもあります。
アメリカでは、共和党が「自立を促すため支給条件を厳しくすべき」と主張し、民主党は「貧困層の安全網として維持すべき」と対立してきました。そのため、政権交代のたびに制度の方向性が揺れるという構造的弱点があります。
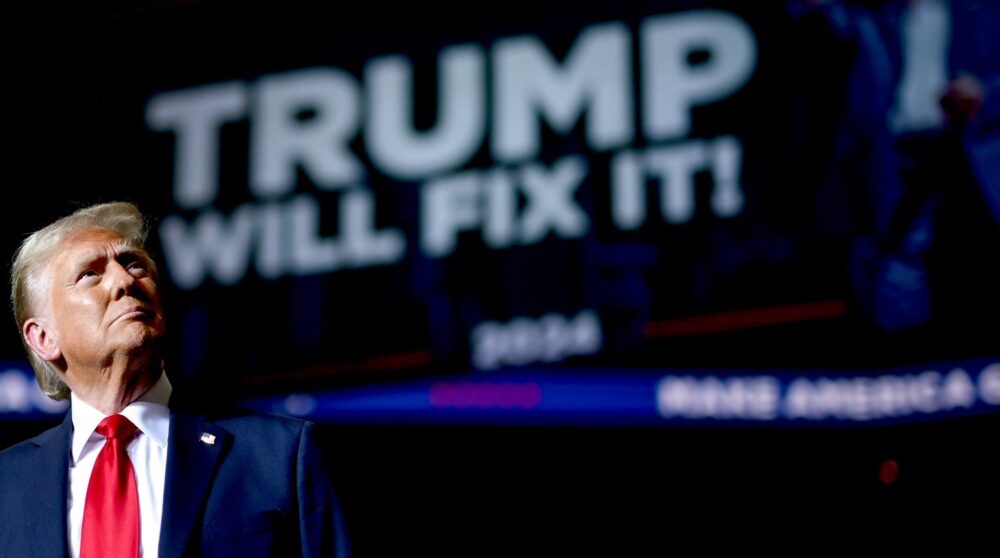
さらに、食品業界や農業団体のロビー活動も影響しています。SNAP対象食品の中には、加工食品大手の利益に直結する商品も多く、「健康的な食材を増やす改革」は常に強い抵抗にあってきました。
結果として、制度は「貧困層の空腹を満たす仕組み」にはなったものの、「健康的な生活を支える仕組み」としては十分に機能していないのが現状です。
SNAP 2.0──“食・農・雇用”をつなぐ新しい構想
最近、SNSなどで話題を集めているSNAP 2.0という提案は、従来の枠を超えた制度改革のアイデアです。
主な柱は以下の3つです。
- 農家支援型の補助金制度:補助金を農家へ直接送金し、規模拡大や生産性向上を支援
- 無料の生鮮食品提供:受給者には農家から直接、果物・野菜・肉・穀物を無料配布
- 雇用連携モデル:農家が拡大する際、SNAP受給者を優先雇用して「支援から自立へ」の橋渡しを行う

この構想の狙いは、「支援される側」と「支援する側」を循環的に結ぶ経済モデルにあります。
もし実現すれば、SNAPは「ただの福祉制度」から「地域経済と健康を動かすエコシステム」へと進化する可能性があります。
MAHA(Make America Healthy Again)との関連──健康を軸にした再構築
この「食から始まる改革」の流れは、ロバート・F・ケネディJr. 厚生長官が掲げるMAHA(Make America Healthy Again)政策とも重なります。
MAHAは、加工食品・医薬依存を減らし、食と生活習慣を通じて国全体の健康を取り戻す運動です。SNAP 2.0の理念と同じく、「健康は医療ではなく食から」という価値観を掲げています。
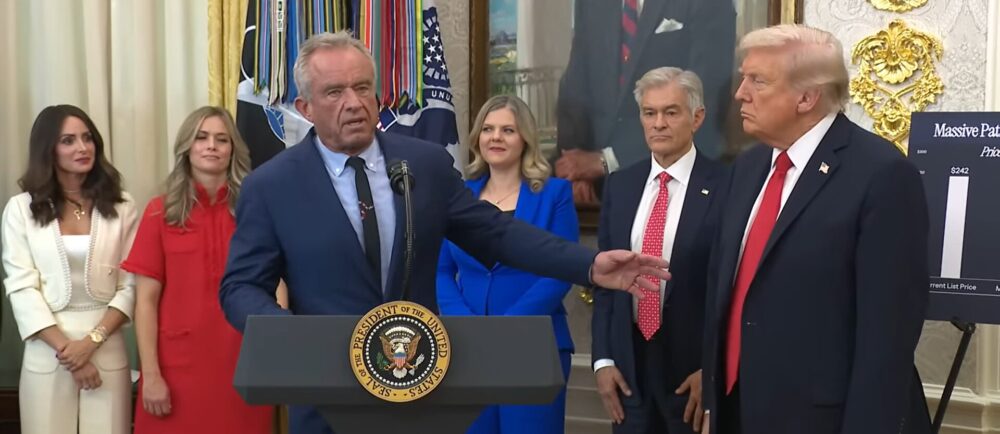
もし両者が連携すれば、貧困支援だけでなく、公衆衛生・農業・雇用を含む包括的な健康政策として展開することができるでしょう。
日本への示唆──食の安全を「制度」として支える視点
日本でも、相対的貧困率は約15%と高く、特にひとり親世帯の貧困率は先進国で最悪水準にあります。所得格差はそのまま「食の格差」として表れ、野菜や肉を十分に買えない家庭も少なくありません。
全国で子ども食堂やフードバンクなどの取り組みが広がっていますが、多くは寄付やボランティアに依存しており、制度としての安定性には課題があります。
アメリカのSNAPのように、食の安全を社会保障の一部として制度化する発想は、日本も取り入れを早急に検討すべきと思います。

たとえば、地元農家の余剰作物を活用し、低所得世帯に健康的な食材を届ける仕組みを作れば、農業支援と福祉支援を両立できます。
食は健康と教育の基本であり、支援の持続性を高めるには、“善意”から“制度”への転換が欠かせません。
日本の政治家は選挙前のパフォーマンスとして子ども支援施設や農家を訪問しますが、再分配の不備による格差問題を本気で解決するつもりがあるのか、疑問に思います。
アメリカのSNAP制度が進もうとしている方向は、「食料支援」を超えた社会改革の一歩です。貧困層の食卓を変えることは、健康寿命や医療費、そして地域経済の循環にも直結します。
これまで先進国では、革新性や科学技術によって国や人々を豊かにすると考えられてきましたが、実は恩恵を受けるのはごく一部の人たちであるという事実に気付き始めています。
その権力構造を壊し、本当の意味での平等を目指しているのがトランプ政権であり、ロバートケネディ長官が取り組むMAHAは、国民の健康や安全を脅かす社会システムの改革です。
この流れは日本にも波及するものと信じ、応援を続けていきたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。
資料:FactChecking.org, TIME, HHS, The Guardian












